UT GroupRecruiting Site
Message 05
2万人を超える
一人一人が、
それぞれ違う。
そこに向き合うから
こそ、
面白い。
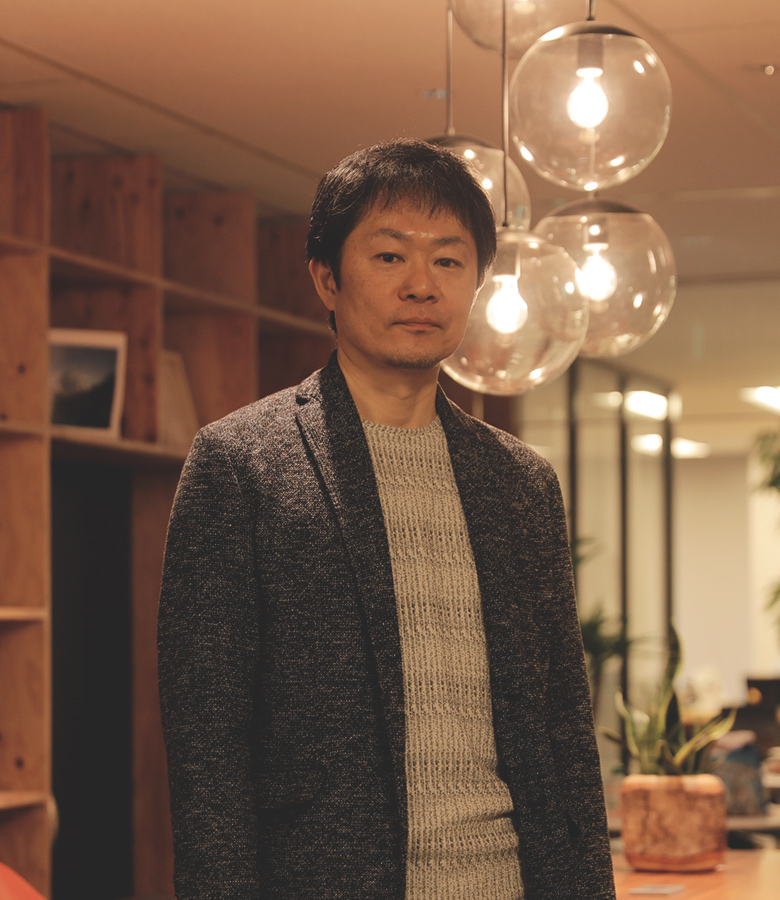
KentaroYamagishi
Profile
山岸 建太郎
サービス開発部門
執行役員
2018年中途入社
大学では心理学を専攻。リクルートに23年間勤務し、適性検査や従業員満足度サーベイなど各種アセスメント開発、研修やEラーニングなどの各種トレーニング開発といったHR領域に携わる。介護職のキャリア教育体系を手がけた縁で介護企業に転職した後、AIをHRに活かすソリューション提供企業へ。クライアントのHR部門と接しているうちに、会社の内部からHRに関わりたいとの思いが募り、UTへ入社した。
01
さまざまな人が
イキイキしている
UTグループの名前は知っていたが、社長と面談して、これほどまでに強い衝撃を受けるとは思ってもいなかった。派遣業界でプラットフォームづくりをやる!? じつは、自分もつくりたかった仕組みだった。
これまでのキャリアでは、ホワイトカラーの上位層約5%しか相手にしてこなかった。しかし、それ以外の層のほうが圧倒的に多い。トータルのHRソリューションを、社会的に弱い立場とされがちな派遣社員に対して本気でやろうとしているのはUTだけだ。その挑戦にコミットしたいと思った。
UTに入社して配属されたのは、プラットフォームを具体化する部門だった。構想自体は1年半ほど前から動き始めており、少しずつ形になっていたが、構想レベルで終わっているものもあり、易々とコトは運ばない。形になっている部分と、思うようには進んでいない部分。その「まだら」な状態を向こう1年で全部仕上げることを、自分が成すべきミッションとした。
まずは数か所の現場を訪ね歩いてみると、ある工場が印象に残った。何種類もの工具を駆使せねばならないのに加え、立ったり座ったりする動作も多い。一言で言うなら、とてもハードな職場だ。ところが、話を聞いたある若手社員は目を輝かせながら、こう言った。
「仕事も一通り全部自分ででき、リーダー的な立場を任されている。もっともっとキャリアアップしていきたい」
人と話すのが苦手な人はあまり語らないものの、集中して仕事に向き合う真摯さが伝わってきた。同じ現場でも、年代もキャラクターも、じつにさまざまな人たちがイキイキとしていた。一つの仕事に対して、働く人のタイプは一つとは限らない。適性を限定してはいけないし、将来の可能性は本人次第で広がっていく。派遣にもダイバーシティはあるのだろうかと懐疑的だったが、現場を見てその考えは覆された。

02
一人一人の個人カルテを
つくりたい
早速、現場で感じたことを反映させるべく、動き始めた。プラットフォームは、一人一人の入口(入社)から出口(キャリアアップ転職)までずっと伴走する重層的な仕掛けである。だから、一人一人がどんな人かをしっかり把握すること、その人に応じた手を打つことが鍵になる。
そのために、アセスメントの企画・開発チームをつくった。採用の段階だけでなく、現場で働いていくさまざまなタイミングで「あの人は、元気に働いているのか?」と状態をしっかり把握し、「あの人のスキルや強みはこれだ」と可視化する。つまり、2万人を超える社員一人一人の「個人カルテ」をつくっていくチームだ。
グループ事業の90%以上の売上を占めるエイムという会社に所属する社員が主たる対象になる。PCP(プロフェッショナル・キャリア・パートナー)という、キャリアアドバイザを専門分化・高度化した新しい職種を設けた。現場にいるマネージャーと両輪になり、技術職一人一人のキャリア形成に付き合うスタイルを目指す。
自身のキャリアにおける数百社以上のコンサル経験から、新たに見えてきたUTの姿もある。急激な成長に、社内のシステムが追いついていない。数字の上では従業員2万人超と大企業だが、中身はまだ仕組みやフローがなく、改善するところがある。次のステージに登るには、業務フロー、マネジメント、コンプライアンスなど、さらに高い次元に変えねばならない。成長の余地が多いことは、UTで働く社員にとって仕事の醍醐味を意味する。
03
社会に1本また1本と、
くさびを打つ
国内外の労働情勢を考えると、今後より拡充させたいのは、外国人技能実習、フリーランサー、IT系、シニアなど新しい人たち・新しい業界への派遣や紹介である。とはいえ、新しい層でのビジネス展開はそう簡単なものではない。新しいフィールドに踏み出す際には、ターゲットをしっかりセグメントしなければ痛い目に遭うことを、前職でもなんどか経験してきた。撤退するという苦渋のジャッジを下して部下たちに辛い思いをさせたこともある。だからこそ、新しいターゲット像は綿密に描いて検討しなければならない。
新しい層に対しても、これまでの派遣業界にはなかった教育機会や多様な就業機会が組み込まれたマネジメントシステムを構築して、社員の給料UPはもちろん、人材としての価値を高めていく。
知る機会、学ぶ機会、キャリアアップする機会などは、プラットフォームで提供できる。それにより、社会的には今はマイノリティーかもしれない人が、もっと充実した世界で生きていけるという思いが、自分の根っこにある。その先には、GDPよりも価値のある、幸福度の高さで先進国となっていく道が開けるに違いない。
そうした挑戦を成功させていく中で、UTの事業を質量とも業界ナンバーワンにしたい。量は、売上や利益。質というのは、技術職で働いている人たちが一人一人充実した生活を送れるための就労機会と生活機会を提供するということだ。質を追求すれば量は上がるし量を追求しながら質を上げるというのが、企業としての正しい事業形である。その正しさを愚直に追い求め、社会に1本また1本とくさびを打っていけるのが、UTという舞台だ。

Message {{id}}
{{nameEn}}